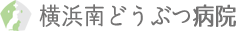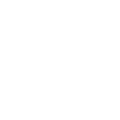新しい超音波診断装置
2023年11月17日
横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」「伊勢佐木長者町」駅・京急本線「黄金町」駅近くにある【横浜南どうぶつ病院】です。
新しい超音波診断装置を導入しました。
富士フィルム(旧日立製作所)の超音波診断装置ARIETTA850です。ARIETTAシリーズの最上位機種となります。メーカーの方曰く、この上位機種の導入例は当院近隣ではまだないとの事でした。
かなり巨大な機器のため、診察室がやや狭くなってしまっています(汗)。
超音波検査は無麻酔かつ非侵襲的に実施可能な検査であり、各臓器をリアルタイムに観察できるという最大のメリットがある検査です。
対象臓器は主に、心臓や腹部臓器(肝臓・脾臓・腎臓・膀胱・消化管・膵臓など)、肺、関節などです。
血液検査機器と同じく、スクリーニング検査に欠かせない機器の一つでありますが、最大の欠点として、実施者(検査する人)の知識・技術の差が最も顕著に出てしまう検査でもあります。
私は超音波診断学に魅了され、北海道大学研修医時代に、画像診断のスペシャリストの先生方の元、コツコツと勉強・トレーニングしてきました。医療機器の性能が良ければ良いほど、綺麗な画像を描出出来ることが出来ますが、綺麗で分かりやすい画像を描出するのはやはり実施者の能力に依存します。これが本当に趣があって楽しいと常々感じています。
最近、色々な種類の最新・最高の医療機器を取り入れていますが、一次診療施設に必要不可欠な迅速かつ的確に検査出来るよう、ますます向上心を持って日々努力していきたいと思っています。

新しい血液検査機器
2023年10月23日
横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」「伊勢佐木長者町」駅・京急本線「黄金町」駅近くにある【横浜南どうぶつ病院】です。
新しい血液検査機器を2機種導入しました。
まず一つ目は「IDEXX プロサイトDx」という自動血球計算装置。
獣医療において最も網羅的な血液細胞の検査項目を測定可能とされています(2021年11月時点)。
・体の防御機構に関わる白血球を、5つに分類
・体の酸素運搬に関わる赤血球を、血液の再生所見を示す網状赤血球を含め測定
・体の止血機構に関わる血小板を、猫の血小板数を含め正確に測定

以前使用していた自動血球計算装置よりも、さらに正確に血液細胞を測定出来る様になりました。
ただし、血液細胞数の測定には大変便利な機器となりますが、血液細胞の形態評価はやはり顕微鏡での観察が重要!という事で、今まで通り血液検査の際は、顕微鏡でコツコツと血液細胞の形態評価を行っております。
2つ目は「IDEXX カタリストOne」という血液化学検査器。
肝臓や腎臓、膵臓に異常がないか、ホルモン異常がないか、体に炎症がないか等を調べる機器です。この検査機器を導入した理由の一つは、腎疾患の指標である尿素窒素やクレアチニンの検査項目と並行してIDEXX SDMAという項目を評価する事が可能であるからです。この項目の測定により腎臓疾患を早期に発見出来るようになりました。
もう一つは、UPCという尿中のタンパク濃度を正確に評価する事が可能であるという点です。こちらも腎疾患の診断治療に非常に有用な項目であるため、この一台で幅広く病気を検出出来るようになりました。

日々進歩する獣医療において、病気の早期発見と早期治療が出来るよう医療機器だけでなく、知識も更新出来るよう努めて参ります。
この他に、超音波診断装置・デジタルX線検査・顕微鏡を新しく導入しました。少しずつご紹介していこうかと思います。
手術室の無影灯をLEDに変更しました
2023年2月9日
横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」「伊勢佐木長者町」駅・京急本線「黄金町」駅近くにある【横浜南どうぶつ病院】です。
日々の診療に手一杯でブログがなかなか更新出来ていませんが、少しずつ更新していきます。まずは昨年秋(!?)に手術室の無影灯をハロゲンからLEDに変更しました(うーん、更新遅いですね)。
当院では手術・処置は丁寧に、確実に、そして迅速にを目標として取り組んでいます。
手術する際に最も重要な設備の一つに無影灯(照明器具の事です)があります。今まで使用していたハロゲンタイプの無影灯は1方向からの照射により術野を確保していましたが、深部の術野において術者(私)の頭が入り込み見難くなったり、無影灯の発熱(私の体が暑くなったり、術野が乾燥したり)で不便を感じる事が多々ありました。
今回導入したLEDタイプの無影灯は2方向から照射する事が可能となり、深部の術野をより明るく照射する事が可能となりました。また発熱もほとんどなく、色温度の調整により手術中の目の疲労軽減が可能となり今までの欠点がなくなりました。
従来のハロゲンタイプの無影灯は、歯科処置用として処置室に移設しています。こちらも無影灯設置により、より充実した歯科処置が可能となりました。
皆様の大切なわんちゃんとねこちゃんに最適な獣医療を提供出来るよう、ますます頑張っていきます。


フィラリア予防にはどのお薬を選んだらいいの?
2022年3月11日
こんにちは。
京急本線「黄金町」駅・横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」「阪東橋」駅近くにある【横浜南どうぶつ病院】です。
蚊が媒介するフィラリア症。この予防のためにお薬を与えますが、内服剤・外用(スポット剤)・注射薬の3タイプがあります。
フィラリア予防がとても大切なワケ
フィラリア症は犬糸状中症とも呼ばれ、文字通り20~30cmもある長い糸状の寄生虫がわんちゃんの血管や心臓に寄生してダメージを与えます。
循環器や呼吸器障害などを引き起こし、命にかかわることもある恐ろしい病気です。
けれども、フィラリア症は確実に予防できる病気です。わんちゃんを命の危険にさらさないためにも、ぜひ適切にお薬を用いてしっかり予防してあげましょう!
フィラリア予防薬の種類とそれぞれのメリット
予防薬には大きく分けて3タイプあります。それぞれのメリットとわんちゃんの性格や体質などに合わせ、適切なお薬を選びましょう。
■内服剤
①錠剤
おやつやフードに混ぜて与えたり、お口を開けて飲み込ませる錠剤です。
食物アレルギーや皮膚が弱いわんちゃんも安心して使用できます。また、お薬の価格が安いこともメリットのひとつです。
②チュアブル錠
お口の中で噛んでから飲み込む錠剤です。
普段、ジャーキーなどの噛んで食べるおやつが大好きなわんちゃんにはおすすめのお薬です。
ただし、食物アレルギーのあるわんちゃんは注意が必要。獣医師に必ず相談しましょう。
■外用(スポット剤)
フィラリアを駆除する成分が含まれた薬液を首の後ろに塗布します。
錠剤やチュアブル錠が苦手、食物アレルギーがあるわんちゃんでも使用できます。
■注射薬
1年間効果が持続するお薬もあり、投与忘れのリスクがないことが特徴です。
ただし、体重に応じてお薬の量を調節する必要から、成長期にある子犬には使えません。
知っておこう! フィラリア予防薬の副作用
お薬には「副作用」がつきものです。
万が一に備えて、フィラリア予防薬の副作用について知っておきましょう。
・ミクロフィラリア反応(ショック反応)
すでにフィラリアの成虫が体内にいる場合に予防薬を使用するとショック反応を起こし、わんちゃんの体に大きな負担がかかることがあります。
・アナフィラキシーショック
投与後、急にぐったりして動かなくなったり、けいれんするなどの異変に気づいたらすぐに動物病院を受診しましょう。
・その他
よろめく、嘔吐、多量のよだれ、食欲不振、下痢や軟便などの症状が挙げられます。
また、スポットタイプの薬剤では皮膚に赤みが出ることもあるので注意しましょう。
そして、コリー系品種(ボーダー・コリー、シェットランド・シープドッグ、ジャーマン・シェパードなど)は、遺伝子変異が原因でお薬を代謝する働きに問題を抱えていることが多く、他の犬種と比べて副作用が出やすいことが特徴です。
お薬を与える前に獣医師に相談しましょう。
フィラリア予防薬についてご相談は当院まで
感染すると命にかかわるケースもあるフィラリア症は、予防薬で確実に予防できる病気です。
予防薬にはさまざまな種類がありますので、わんちゃんの性格や体質に合わせ、適切なお薬を選びましょう。
副作用などについて不安があればご相談ください。
フィラリア予防に効果的なタイミングは「いつ」?
2022年2月20日
こんにちは。
京急本線「黄金町」駅・横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」「阪東橋」駅近くにある【横浜南どうぶつ病院】です。
わんちゃんの病気のうち「フィラリア症」は広く知られていますね。
フィラリア症は蚊が媒介する病気なので、“予防薬は夏になってからでも大丈夫でしょう”と考えていたら、それは大きな間違い。
「5月」が予防を始める効果的なタイミングなんです。
フィラリア症は100%予防できる病気です
フィラリア症は、「イヌフィラリア(犬糸状虫)」の幼虫に寄生された蚊に刺されることで感染する寄生虫疾患です。
フィラリアの幼虫はわんちゃんの体内で20~30cmの長さにまで成長し、やがて心臓や肺動脈に寄生。すると肝臓肥大、腹水、浮腫、肺動脈の詰まりなどの症状が現れます。
場合によっては心臓の弁にまでフィラリアがからまり、急死することもある恐ろしい病気です。
しかし、フィラリア症は正しくお薬を与えれば、確実に予防できます。
“気づかないうちに感染していた…”ということがないよう、きちんとした対策が大切です。
フィラリア予防は「5月」から、がベストな理由
蚊の活動時期は季節よりも気温が大きく関係します。
近頃は温暖化の影響で蚊が活動を始める時期が早まり、すでに4月には蚊が飛んでいる姿を見かけることも多くなってきました。
つまり、4月にはフィラリアに感染する可能性があるということになりますが、すぐに予防薬を与える必要があるのかというとそうではありません。
フィラリアの幼虫は犬の体内に入り込んでから3~10日後に脱皮し、体中に移動できる段階に成長します。
フィラリアの予防薬にはこの段階の幼虫を100%駆除する効果があります。そこで蚊が姿を見せる4月よりも、1ヶ月後の5月からお薬を与え始めることが予防のベストタイミング。
そして蚊の活動が弱まる11月から1ヶ月後の「12月」までお薬を続けましょう。
フィラリアの予防薬を与える前には必ず血液検査を!
毎年、蚊の活動時期の初めに血液検査を受けて、フィラリアの感染確認を行いましょう。
フィラリアの予防薬は、獣医師の指導のもとに使用しなければならないお薬です。
与える前には血液検査を行い、フィラリアの感染の有無を確認しなければ処方することができません。
なぜなら、すでにフィラリアの成虫が大量に存在している場合、予防薬でショック反応を起こす危険があるためです。
フィラリア予防は毎年行いましょう
蚊が媒介するフィラリア症は、お薬を正しく与えれば100%防げる病気です。
そして予防薬を与える前には必ず血液検査を受けてください。
当院では、わんちゃんの健康状態をはかるうえでとても重要な検査として血液検査を位置付けています。
フィラリアの感染確認とあわせ、病気の早期発見にも役立ちますよ。
ねこちゃんのQOL向上に。去勢・避妊手術で病気予防
2022年1月15日
こんにちは。
京急本線「黄金町」駅・横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」「阪東橋」駅近くにある【横浜南どうぶつ病院】です。
この先、ねこちゃんに子どもを産ませる予定がなく、穏やかに過ごさせてあげたいと考えていたら去勢・避妊手術を検討してみませんか?
去勢・避妊手術には繁殖を避ける目的だけでなく、病気予防のほか、問題行動などを抑える効果があるんです。
繁殖を避けるだけじゃない。去勢・避妊手術の目的
ねこちゃんの去勢・避妊手術は繁殖を避けるため以外にも、性ホルモンが関係して発症するいくつかの病気を予防したり、発情期にともなう「ストレス」を取り除くという効果があります。
また、外とおうちを自由にお出かけしているねこちゃんが“望まぬ妊娠”をしてしまう、またはどこかで不幸な子猫を増やしてしまっているケースがあります。
こうしたことを避けるためにも去勢・避妊手術という選択肢について知っておくことはとても重要です。
去勢・避妊手術で予防できる病気とメリット
ねこちゃんの去勢・避妊手術で予防できる病気は以下のものがあります。
■男の子の場合
・精巣腫瘍
■女の子の場合
・乳腺腫瘍
・子宮蓄膿症
・卵巣や子宮の腫瘍 など
■男の子、女の子共通
・猫免疫不全ウイルス感染症(猫エイズ)
・猫白血病ウイルス感染症
病気の予防以外にも、男の子の場合にはスプレー行動(マーキング)・攻撃行動(ケンカ)、女の子の場合には発情行動(鳴き声、精神不安定、おしっこの回数が増える)といった発情期にともなうストレスを取り除いて、ねこちゃんのQOL(生活の質)を高めるというメリットもあります。
去勢・避妊手術を受けるよいタイミング
ねこちゃんの去勢・避妊手術は、最初の発情を迎える「生後6~7ヶ月」頃に行うのが一般的です。最初の発情を迎える前に手術を受けた場合、先に挙げた病気を高い確率で防ぐことができるからです。
特に、乳腺腫瘍は1歳以降に避妊手術を受けた場合にはあまり予防効果がないとされているので、タイミングを逃さないように気を付けましょう。
当院では、避妊・去勢手術は基本的に生後6ヶ月以降に行います。
若齢期~高齢期にあるねこちゃんの手術をご希望の場合には、まずはご相談ください。
当院では飼い主さんの気持ちも受け止め、慎重に去勢・避妊手術を行っています
去勢・避妊手術にはいくつかの病気を予防する効果があります。
そのほか、発情期にみられる問題行動やそれに伴うストレスも取り除くことができ、ねこちゃんのQOLがアップするというメリットもあります。
“手術”と聞くと心配になってしまう飼い主さんもいらっしゃることでしょう。
当院では飼い主さんの不安にもじっくりと耳を傾け、きちんと説明することを大切にしていますので、いつでもご相談ください。
また、ねこちゃんに負担をかけない手術を心がけていますのでご安心ください。
外へお出かけするねこちゃんはノミ・マダニ予防を!
2021年9月13日
こんにちは。
京急本線「黄金町」駅・横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」「阪東橋」駅近くにある【横浜南どうぶつ病院】です。
ねこちゃんが後ろ足で首のあたりをかいている姿をよく見かけませんか?
もしかしたらノミやマダニが寄生しているのかもしれません。
外へ自由に行き来させているねこちゃんは特に注意が必要です。
いつ、どこでノミやマダニが寄生するの?
ノミやマダニは主に草むらや木の上、野生動物の体毛を住みかに生息しています。
そのため、おうちと外を自由に行き来させているねこちゃんの場合、お出かけの途中でノミやダニを連れて帰ってきてしまう
ことが考えられます。
また飼い主さんが知らずに持ち込んでしまうケースや、一緒に暮らしている他の動物からうつってしまうケースもあるようです。
人間も要注意! ノミ・マダニがねこちゃんに媒介する病気
ノミやマダニに寄生されるとかゆみだけでなく、ねこちゃんにさまざまな病気をもたらすことがあります。
・猫ヘモプラズマ感染症
・アレルギー性皮膚炎
・瓜実条虫(サナダムシ)
・ライム病
・日本紅斑熱
・重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
・猫ひっかき病
なかでも、ねこちゃんに発熱、食欲不振、お腹が膨らむなどの症状がみられる場合、ひどい貧血が主な症状である「猫ヘモプラズマ感染症」が疑われます。
また「猫ひっかき病」は人間にも感染し、まれに麻痺や脊髄障害などを引き起こす病気です。
さらに「重症熱性血小板減少症候群」は、人間の死亡例も確認されている恐ろしい病気ですので、特に気を付けましょう。
ノミやマダニの予防には定期的なお薬投与が効果的
ノミやマダニからねこちゃんを守るにはお薬による予防が効果的です。
首の後ろに薬剤を垂らすスポットタイプのお薬や、飲み薬があります。
予防効果を高めるためには定期的にお薬を与えることが大切です。
また、すでに寄生されている場合は駆除剤の投与やノミ取り首輪でしっかり駆除しましょう。
そして、普段から目の細かい「ノミ取りクシ」でブラッシングすることをおすすめします。
ただし、ノミやマダニを捕まえても絶対に潰さないこと。
潰すと卵や寄生虫が飛び出し広範囲に広がります。粘着テープにくっつけて、中性洗剤を溶かした水に沈めて駆除しましょう。
快適な毎日のために予防と駆除を心がけて!
ノミやマダニからもたらされる病気を防ぐには、ノミ・マダニの寄生を「予防」することが大切です。
特に外へお出かけするねこちゃんは気を付けてあげましょう。
もしも寄生されてしまった場合は、できるだけ早めの駆除が必要です。
当院は土日祝日も診療していますので、気づいた時はいつでもご相談くださいね。
去勢・避妊手術で防げるわんちゃんの病気
2021年8月9日
こんにちは。
京急本線「黄金町」駅・横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」「阪東橋」駅近くにある【横浜南どうぶつ病院】です。
将来、わんちゃんに子どもを産ませる予定がなければ、去勢・避妊手術を検討してみませんか?
去勢・避妊手術には繁殖を避ける目的だけでなく、年を重ねるにつれて発症リスクが高まるいくつかの「病気」に対して予防効果があるんです。
去勢・避妊手術は繁殖を避けるためだけではありません
わんちゃんの去勢・避妊手術は繁殖を抑制する目的以外にも、性ホルモンが影響してわんちゃん自身が感じる発情期のストレスを取り去ったり、性ホルモンに由来する病気を防ぐために行われます。
また、海外の統計ですが、手術を受けたわんちゃんのほうが長生きするという調査結果もあります。
去勢・避妊手術で予防できる病気
わんちゃんの去勢・避妊手術で予防できる病気は以下のものがあります。
■男の子の場合
・会陰ヘルニア
・前立腺疾患
・精巣腫瘍 など
■女の子の場合
・乳腺腫瘍
・子宮蓄膿症
・卵巣や子宮の腫瘍 など
病気の予防以外にも、男の子の場合にはマーキングの減少・攻撃行動の減少・ストレスの減少、女の子の場合には攻撃行動の減少・発情行動(鳴き声、精神不安定)がなくなる・偽妊娠がなくなるといったメリットもあります。
去勢・避妊手術を受けるベストな時期は?
一般的に去勢・避妊手術を受ける一番良い時期は「生後半年~1歳まで」とされています。
初めての発情を迎える前に手術を受けた場合、先に挙げた病気を高い確率で予防することができるからです。
たとえば乳腺腫瘍の発症リスクは80~90%も下がります。
当院では、避妊・去勢手術は基本的に生後6ヶ月以降に行います。
若齢期~高齢期にあるわんちゃんの手術をご希望の場合には、まずはご相談ください。
当院では慎重に去勢・避妊手術を行っています
去勢・避妊手術は性ホルモンが影響して発症する病気のリスクを低減できます。
そのほか、発情期における問題行動やわんちゃん自身が感じるストレスも予防することができ、わんちゃんも飼い主さんも穏やかに過ごせるというメリットも。
大切なわんちゃんに“手術”は心配…という飼い主さんのために、当院では疑問や不安についてきちんと耳を傾け、丁寧に説明することを大切にしています。
何でもお気軽におたずねください。
また、わんちゃんの負担をできる限り減らした手術に努めているのでご安心ください。
室内飼いのわんちゃんもノミ・マダニ予防しましょう
2021年7月20日
こんにちは。
京急本線「黄金町」駅・横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」「阪東橋」駅近くにある【横浜南どうぶつ病院】です。
お散歩以外、おうちで過ごすことの多いわんちゃんも気を付けてほしいのが「ノミ」「マダニ」の寄生です。
ノミ、マダニは体がかゆくなるだけではなく感染症の原因にもなるので、しっかり予防しましょう。
こんな仕草はノミやマダニが寄生しているサイン
おうちのわんちゃんに以下のような様子が見られませんか?
もしかしたらノミやマダニが寄生しているかもしれません。
- しきりに顔や体をかいている
- 前歯で体のあちこちを噛んでいる
- かゆいのか体を地面にこすりつけている
- 地肌にぽつぽつと赤いところがある
- 毛の中にフケのような黒色の塊がある
- 皮膚に炎症(ジュクジュクの状態)がある
- 体毛の一部が抜けていたり、薄くなっているところがある
かゆいだけじゃない。ノミ・マダニが媒介する病気
ノミやマダニの感染経路は主に“外”から。
草むらに潜むノミやマダニが、お散歩で通りかかったわんちゃんに飛び移って寄生します。
ほかには、飼い主さんの服にくっついていて家の中に持ち込まれたり、野良猫や他の犬から移ったりすることも……。
ノミやマダニに刺されるとひどいかゆみやアレルギー性皮膚炎の原因になります。
さらに、バベシア症、瓜実条虫(サナダムシ)、ライム病、日本紅斑熱、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)などの病気を引き起こすこともあります。
特にマダニが媒介する日本紅斑熱、SFTSは人間にも感染するので注意が必要です。
ノミ・マダニ予防には予防薬が効果的
ノミやマダニからわんちゃんを守るお薬があります。
錠剤のほか、最近はおやつ感覚で摂取できるチュアブルタイプのお薬や首の後ろに薬液を垂らすスポット剤が人気です。
お薬は月に1回、継続して与えることが必要です。
ノミやマダニが増える夏までにしっかり予防しましょう。
フィラリアと一緒に5月からの予防がおすすめです。
また、シャンプーやブラッシングできちんとお手入れする、お散歩から帰ってきたらノミやダニがいないかをチェックするといったことを普段から心がけましょう。
実は身近にいるノミ・マダニに注意しましょう
室内飼いのわんちゃんもお散歩などの外出先でノミやダニと接触してしまうことがあります。
ノミやマダニは皮膚炎や感染症を引き起こすことがあるので、寄生しないように定期的にお薬で予防することが必要。
市販薬もありますが医薬部外品にあたるので、より効果が高い動物病院の処方薬がおすすめです。
そしてノミやマダニを増やさないために、シャンプーやブラッシングなどの日ごろのケアや、おうちの中もできる限り清潔
に保ちましょうね。
犬・猫にあげてはいけない食べ物とは?
2021年2月25日
こんにちは。
黄金町駅・伊勢佐木長者町駅 の 動物病院「横浜南どうぶつ病院」です。
わんちゃん・ねこちゃんには、食べると危険な食材があります。
それは犬猫ともに、ほぼ共通していて、有名なものではタマネギやニラといったネギ類があります。
昔はインターネットもなく、そういった情報が広く知られていなかったので、わんちゃん・ねこちゃんが人間と同じものを食べていた時代もありました。
今となってはわんちゃん・ねこちゃんの健康にとって、非常にハイリスクでしたね。
基本的に、人間と同じものを食べると塩分の摂りすぎになってしまいます。
今や塩分過多は、命に関わる重篤な病気につながるリスクがあることは常識。みなさん気をつけているとは思いますが、わんちゃん・ねこちゃんが欲しがるからといって飼い主さんが食べているものを簡単に分けてあげてはいけません。
ここ10~20年でもわんちゃん・ねこちゃんの寿命が圧倒的に延びていますから、情報の広がりとともに様々な健康を害するリスクを回避できるようになってきたといえるでしょう。
●ネギ類(タマネギ、ニンニク、ニラ、ネギなど)
ネギに含まれる成分には、わんちゃん・ねこちゃんの赤血球を破壊する作用があるので危険です。ネギは加熱・調理しても毒性が消えないので要注意です。
特にタマネギは万能食材として色々なものに使われています。スープやおみそ汁など、入っているのを忘れて、うっかりあげてしまうことがないように気を付けましょう。
●チョコレート類(ココア、コーヒー、コーラ、お茶など)
わんちゃん・ねこちゃんともに、カカオ・カフェインを構成する成分によって下痢や嘔吐、痙攣を引き起こすことがあります。
チョコレートは急性心不全を起こす恐れが高いので、特にわんちゃんには絶対にあげてはいけません。
●消化不良をおこしやすい食品
エビ、タコ、イカ、カニ、こんにゃく、しいたけ、たけのこなどは、わんちゃん・ねこちゃんともに消化不良をおこしやすい食品です。
●牛乳
牛乳はカルシウムや乳酸菌などが豊富で、人間にとってはヘルシーな食品ですね。
ですが、わんちゃの場合は特に、牛乳の成分を分解する酵素が不十分なため、軟便や下痢を起こしやすいといわれています。
ただし個体差があり、牛乳が好きな子もいます。
●アワビなどの貝類
海そうをエサにしている貝類がもっている毒素は、わんちゃん・ねこちゃんともに皮膚病を引き起こしやすい成分です。
わんちゃん・ねこちゃんにあげてはいけないものなど、食べ物に関する疑問や不安なども、お気軽にご相談ください。
かかりつけ獣医と一緒に、わんちゃん・ねこちゃんの健康を末永く守っていきましょう。